明日予定されていた鎌倉の花火大会ですが、
海上の高波と強風による影響で打ち上げる船の安全な航行が不可能なため、
中止と発表されました。
確かにここ数日は台風の影響もあり、藤沢市内では暑さ以上に強風から身を守るのに大変でした。
私はよく釣りをしに海に行きますが、海の状況は、地上の感覚とは全く違うところがあります。
晴れていても、風がつよく、波が高いときは近づけません。
当日の天気に関わらず中止ということなのですが、前日の判断なので余程のことなんだと思います。
特に行く予定があったわけではありませんが、予備日もないということで、楽しみにしていた方も残念かと思いますが、花火を準備していた花火師さんや関係者の方のことを考えると辛いところです。
安全第一なので、仕方がありませんね。
以前、鵠沼海岸の花火大会に行ったことがありますが、海から上がる花火は格別でした。
これまで船の上から打ち上げる大変さを知らずに見ていましたので、今回それを教えてもらいました。
確定申告が必要な人
さて、最近は、働き方の多様化や雇用の延長も後押しし、給与と副業、給与と年金のように複数の収入を得ている方が増えてきた印象です。
そこで気になるのが確定申告が必要かどうか。
今まで会社の年末調整や年金の源泉徴収だけで済んでいた人が一から確定申告をするのは、結構大変です。
eーtaxやスマホでの申告が普及し、手続きのハードルはだいぶさがってきました。
それでも、そもそも申告が必要かどうかで悩まれている方がいます。
そういう人のために、確定申告の時期に税理士への無料相談会や税務署への相談コーナーがあります。
相談に来る方の中で、そもそも申告が必要がない方も一定数います。
そこでよくある申告不要のケースをあげます。
1.給与をもらっていて、副業での所得が20万円以下
2.給与と年金をもらっていて、公的年金の所得が20万円以下
3.給与と年金をもらっていて、公的年金の収入が400万円以下で、給与の所得が20万円以下
所得というのは、収入から経費や法律で決められた控除額を差し引いた金額をいいます。
この所得という概念を理解しないと、ほぼ全てにおいて税金の計算はできなくなります。
私としては、この所得の考え方をどうにかして浸透させたいです。
ちなみに、給与所得20万円以下というのは、収入85万円以下で、公的年金の所得が20万円以下というのは、年収が80万以下(65歳以上の方は、130万円以下)の方です。
と言われてもわかりにくいですね。
(フローチャートにして説明することが多いですが、ここでは割愛します。)
この所得という言葉自体が、普段から確定申告している方でもあまり馴染みがないようです。
番外編
他によくあるケースとして、
1.今年は医療費が多かったので、確定申告して還付を受けたい。
でもそもそも源泉徴収されている金額がないので、確定申告をしても還付する金額がない。
2.毎年確定申告はしている。
今年は医療費が多かったので、医療費を払った分税金が戻ってくると思っているが、源泉徴収されている金額が少ないので、それ以上は戻ってこない。
医療費=還付という考えが間違っているとは思いませんが、このケースは、説明しても中々理解していただけません。
(私の説明がよくないこともあるかもしれませんが)
最近、小学校の租税教室で講師をして思うことですが、国民の三大義務の一つである納税について、税金の仕組みだけでなく、自分が所得税の納税者となった場合に、税金をどのように計算するかみたいなのは、eーtaxランニングみたいなのを使って社会人になるまでに教えるべきなのではと思います。
簿記の知識は必要なく、算数の延長で教えられます。
(次に、誰が教えるのかという問題がありますが。)
まとめ
令和7年で給与所得控除の金額や基礎控除の金額に変更があり、計算方法は複雑になるばかりです。
結局のところ、源泉徴収されている方で、損したくないという方がいる場合は、今後も還付申告すると税金は戻るかという相談の方が増えていく気がします。
そういう方は、e-taxなどを使って計算されることをお勧めしますが、どうしてもわからない場合は、やはり税務署か税理士の無料相談会で聞いてみることをお勧めします。
それでは、また。

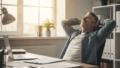

コメント