私自身、基本的には、全て目の前に紙の書類を置いて、それをもとに業務を行っていました。
データでもらっても必ず印刷していました。
それくらいアナログ派でした。
決してアナログを否定するつもりはありません。
ただ、いつからか書類と仕事をすることが税理士の仕事ではないと思うようになり、経営に必要な数字をできるだけはやく共有し、未来をつくるお手伝いがしたい強く思うようになりました。
そのためには、可能な限りデジタル技術を活用して、お客様の意思決定スピードをあげるサポートが必要です。
まずは、費用負担も少なく、すぐにできることからはじめてみましょう。
紙の書類が増えてきて、置き場に困る。
書類をよくなくす。
書類の整理に時間がかかる。
税理士から都度資料の依頼が来る。
経理関係の書類を整理し、税理士とのコンタクトをスムーズに行い、経営や意思決定の相談に時間を使いたい。
そんな普段の書類を電子で保存できたらいいなーと思ったら、
「電子帳簿保存法」に基づく保存方法に取り組み、上手くいけば生産性向上や業務の効率化へにつながるチャンスと言えます。
今回は、「電子帳簿保存法」の中でも、電子保存のスタートして、取り組みやすい「電子取引データ」の保存について、その概要を分かりやすく解説していきたいと思います。
1.そもそも「電子取引データ」って、何を保存するの?
電子帳簿保存法において保存が必要な「電子取引データ」とは、紙でやりとりしていた場合に保存が必要だった書類(例えば、注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、請求書など)に相当する電子データを指します。
•重要なポイントは、「データでやりとりしたもの」が対象であるという点です。
紙で受け取った書類をわざわざデータ化する必要はありません。
•また、データを「受け取った場合」だけでなく、「送った場合」にも保存の義務がありますのでご注意ください。
•保存するファイル形式に規定はなく、PDFに変換したものやスクリーンショットでも問題ありません。
2.どうやって保存すればいいの?3つのポイント!
電子取引データを保存する際には、主に以下の3つのポイントを満たす必要があります。
ポイント①:改ざん防止のための措置をとる!
保存されたデータが後から改ざんされることを防ぐための措置が求められています。
具体的な方法としては、以下のいずれかを選択できます。
•タイムスタンプを付与する:データの作成日時を証明し、それ以降の改ざんがないことを証明する方法です。
•訂正・削除の履歴が残るシステム等でデータの授受・保存をする:クラウドサービスなど、データの履歴管理機能を持つシステムを利用する方法です。
•改ざん防止のための事務処理規程を定めて守る:これは、システム費用などをかけずに導入できる方法として特に注目されています。(⇒オススメ!!)
国税庁のホームページには、この事務処理規程のサンプルが掲載されていますので、参考にすると良いでしょう。
ポイント②:検索できるようにする!
保存された電子取引データは、税務調査などで必要な際に速やかに探し出せるよう、検索できる状態にしておく必要があります。
•最低限、「日付」「金額」「取引先」の3つの項目で検索できることが求められます。
•また、ディスプレイやプリンタを備え付けて、税務職員から求められたデータを速やかに出力できるようにしておく必要もあります。
専用システムがなくても大丈夫!簡易な検索方法
専用のシステムを導入していなくても、以下の簡易な方法で検索要件を満たすことができます。
•表計算ソフト等で索引簿を作成する方法:Excelなどの表計算ソフトを使って、日付、金額、取引先などをまとめた索引簿を作成し、それを利用してデータを検索する方法です。
索引簿のサンプルも国税庁HPに掲載されています。
•規則的なファイル名を付す方法:電子取引データのファイル名に「日付・金額・取引先」を規則的に入力し、特定のフォルダに集約しておくことで、フォルダの検索機能を活用する方法です。
◦例:20240331_110000_(株)霞商店.pdf のように、日付、金額、取引先をファイル名に含めます。
ポイント③:税務調査での提示・提出に対応する!
税務調査の際に、税務職員から電子取引データのダウンロードを求められた場合には、速やかにその電子取引データを提出できる体制を整えておく必要があります。
3.もし「まだ対応できてない…」という場合でも大丈夫?猶予措置について
「システム整備が間に合わない」など、原則的なルールに従って電子取引データを保存するための環境が整っていない「相当の理由」がある場合には、猶予措置が適用される可能性があります。
ただし、システム等の整備が整っていて原則的なルールに従った保存ができるにもかかわらず、資金繰りや人手不足といった特段の事情がないのにルールに従って保存していない場合は、猶予措置は認められません。
猶予措置の対象となるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
1.ディスプレイやプリンタを備え付けて、税務職員に指定されたデータを速やかに出力できるようにしていること。
2.取引の「日付・金額・取引先」で検索できること。
3.電子取引データのダウンロードの求めがあった場合に、求めに応じられること。
4.以下のいずれかの条件に当てはまること。
◦基準期間(2年前)の売上高が5,000万円以下である。
◦電子取引データをプリントアウトした書面を、日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出できること。
まとめ・もっと詳しく知りたいときは?
電子取引データの保存義務化は、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の大きな流れの一環です。
まずは「改ざん防止」と「検索機能」の二つの柱をしっかりと押さえることが重要です。
簡易な方法や猶予措置も活用しながら、自社に合った形で対応を進めていきましょう。
より詳しい情報や、各種サンプルのダウンロードは、国税庁ホームページの「電子帳簿等保存制度特設サイト」に掲載されていますので、ぜひご確認ください。!
弊所は、クラウド会計を積極的に活用しています。
クラウド会計の活用は、電子保存に取り組むうえで、大きなメリットとなります。
お客様でもお一人ですべて電子保存に取り組み、ペーパーレス化を実現し、
経営に生かすための経理体制を整えた実績があります。
ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
それでは、また。
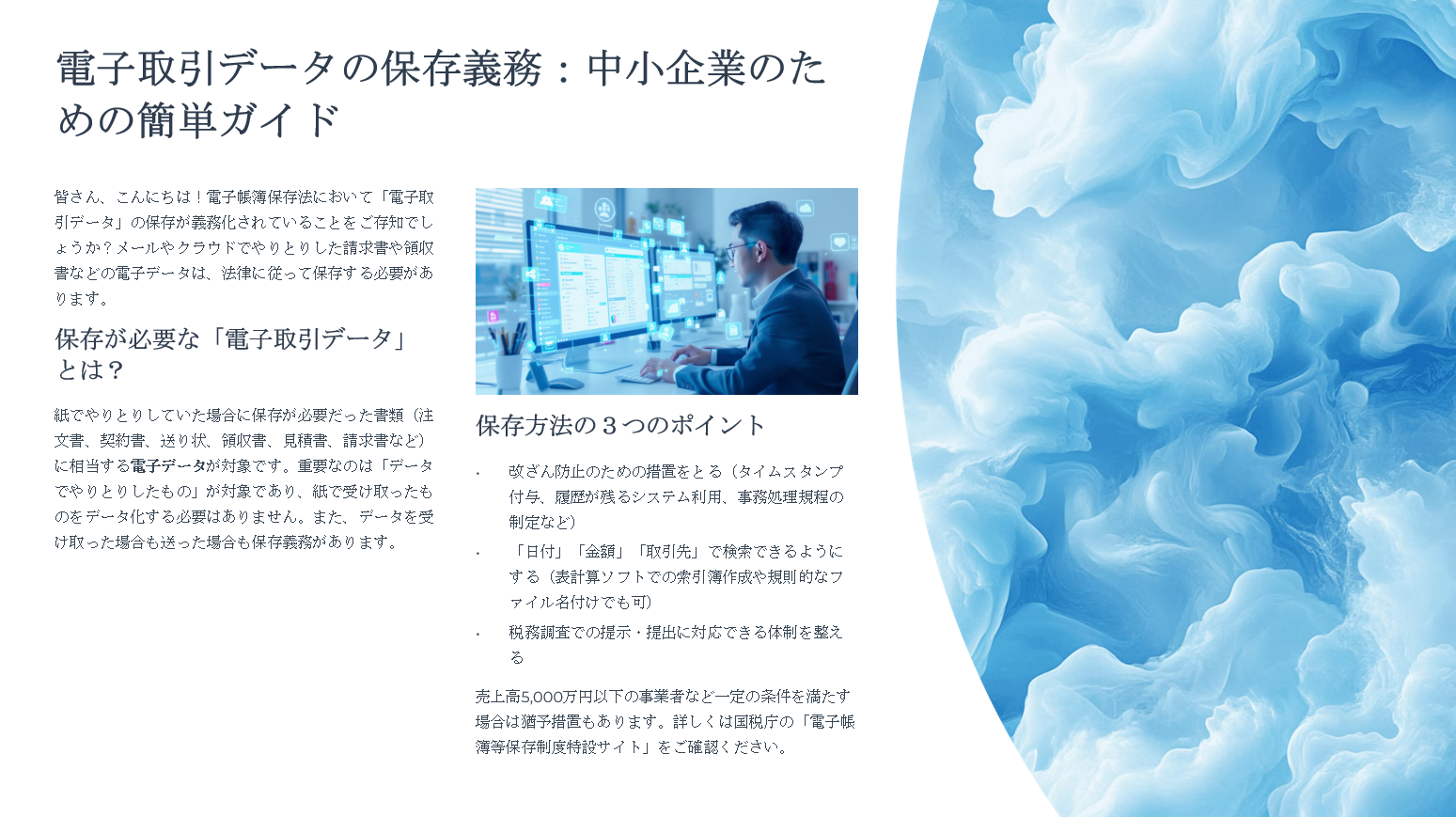

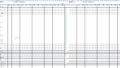
コメント