昨日に引き続き「小規模企業白書」を読みました。
今回の小規模企業は、前回の中小企業と異なり、より身近で、地域経済を支えている、地域に根ざす企業、悪くいえば地域の外的要因に左右されやすい、依存しやすいとも言えるかなで、持続的、継続的経営に必要なものが見えてきました。
今回は、余計な学習知能を取り入れず、白書に記載された内容だけでまとめることができる「notebook LM」でまとめてみます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
経営者の皆様、日々の事業運営、誠にありがとうございます。
先行き不透明な時代、深刻な人材不足やコスト増加に加え、特に人口減少が進む地域では顧客の減少といった厳しい経営環境に直面されている方も多いかと存じます。売上高や営業利益を維持していくことさえ難しくなりつつある状況がデータからも示唆されています。
しかし、小規模事業者の皆様は、全国各地の地域経済の成長・発展に不可欠な存在であり、地域に根ざした事業を通じて雇用を生み出し、付加価値を創造しています。そして、厳しい環境下でも持続的に発展するためのヒントが、最新の調査データから見えてきています。
今回は、経営者の皆様にぜひ知っていただきたい、経営力向上のための重要なポイントをブログ記事風に要約してご紹介します。
1.「強み」を磨き、新しい「販路」を拓く!
顧客減少傾向にある中で、売上確保・拡大は喫緊の課題です。そのためには、まず「自社の強み」を明確にし、競合他社との「差別化」を図ることが重要です。調査では、差別化を意識している事業者ほど売上高、営業利益、顧客数が増加する傾向が見られました。
具体的な差別化の要素として、「高い品質」「希少価値・プレミアム感」「地域資源・文化の活用」「事業背景(ストーリー性)への共感」「顧客との密着性・コミュニケーション」といった要素が売上高の増加につながる可能性が示唆されています。特に地方圏では、地域資源・文化の活用や顧客との密着性・コミュニケーションによる差別化が意識されている様子がうかがえます。事例でも、万年筆専門店が社長自身をブランディングしてストーリーを売る、塗料会社が1回塗りの高耐久性塗料を開発する、手袋製造業者が職人技術を活かしたオーダーメイドと手厚いアフターフォローで高付加価値化する、こけし製造業者が海外ニーズに合わせて現代風にアレンジする、酒造業者が地域のファンを増やすために定期便やイベントで交流するといった取り組みが成果につながっています。
また、新たな顧客を獲得し、販路を拡大することも不可欠です。 新規顧客獲得に向けては、以下の点が重要と考えられます。
・市場や顧客ニーズなどの外部環境を把握すること。特に競合他社の特徴・動向や個人消費の特徴・動向を意識することが重要である可能性が示唆されています。経営戦略や新規事業検討の際に外部環境を重視している事業者の方が、新規顧客数が増加する割合が高い傾向が見られます。
•新しい製品・サービスを開発すること。
•情報発信を強化すること。特にSNSの活用は新規顧客獲得に有効である可能性が示唆されています。小規模事業者の4割がSNSを活用しており、製品・サービスの紹介、顧客とのコミュニケーション促進、新規顧客開拓など幅広い目的で活用されていま。SNSは遠隔地の顧客や潜在顧客とのつながりにも効果を発揮している可能性があります。事例でも、SNSでの情報発信やPR強化が新規顧客獲得・売上増加に繋がったケースがあります。
地域資源の活用に取り組む小規模事業者は、地域の既存の特産物などを活用して自社商品等の付加価値を高めたり、地域の魅力の発信に貢献したりしている可能性があります。地域資源活用における課題としては、「販路開拓」や「製品・サービスのコンセプトづくり」などが挙げられています。
2.限られた「経営資源」を強くする!
小規模事業者には、使える時間も資金も人材も限りがあります。その限られた資源をいかに効率的に、そして効果的に活用するかが、持続的発展には欠かせません。
•「人材確保・定着」「副業・兼業人材」の活用も示唆されています。事例でも、副業・兼業人材を活用して商品開発や販路開拓の課題を解決したケースがあります。
•「価格転嫁・適切な価格設定」も重要な経営課題です。物価や人件費の上昇分を適切に価格に反映させるためには、自社の「原価構成」や「利益」を正確に把握しておくことが不可欠です。多くの小規模事業者では、経理事務の従事人数が少なく、帳簿作成頻度が低い状況が見受けられます。利益を確保するためにも、意識的に経理事務に取り組み、自社の経営状況を数字で把握する習慣をつけましょう。事例では、支援機関の財務分析に基づき販売方法を見直し、収益改善を実現したケースが紹介されています。
•「DX・デジタル化」による業務効率化は、労働生産性向上に貢献します。特に「顧客データの一元管理」、「営業活動や受発注管理のオンライン化」、「紙書類の電子化・ペーパーレス化」といった取り組みが業務効率化につながる可能性が示唆されています。事例では、デジタルツールを活用してベテラン役員のノウハウを形式知化し、次世代への承継や業務効率化を実現したケースがあります。
3.羅針盤となる「経営計画」を持つ!
目先の業務に追われていると、つい後回しになりがちな「経営計画」の策定。しかし、計画を立て、その進捗を管理し、定期的に評価・見直しを行うといった「運用」に取り組むことで、業績及び集客力の向上につながる可能性が示唆されています。当初の目的以外の副次的な効果が得られる可能性もあります。また、計画があったからこそ、補助金や融資の獲得につながった事例もあります。人材が限られる小規模事業者においては、時間的な制約から計画策定に着手できていない状況も見られます。そのような時は商工会・商工会議所、中小企業診断士といった「支援機関」を積極的に活用する**ことが有効です。専門家との対話を通じて構想を整理・明確化し、計画に落とし込むこと、外部の視点や専門家の知識・アドバイスを取り入れることで、より実現性の高い計画を策定できるでしょう。災害時等の事業継続力強化計画策定においても、支援機関の伴走支援が有効であった事例があります。
4.地域とともに発展する可能性
小規模事業者は、地域経済にとって欠かせない存在であり、地域の課題解決への貢献も期待されています。 実は、地域の社会課題解決に「営利事業として」取り組んでいる事業者は、そうでない事業者と比べて業績や集客力が向上している割合が高いという調査結果も出ています。地域にどんな社会課題があるか分からない、という事業者も多いようですが、地域の課題に目を向け、探索すること、地域の課題をビジネスの視点で見つめ直すことで、新たなビジネスチャンスが生まれる可能性を秘めているのです。買物困難地域で移動販売事業を行い、地域のニーズに応えることが事業の継続・拡大に繋がっている事例があります。地域の社会課題解決に向けた事業は、収益計画やビジネスモデルの評価が難しいといった理由で資金調達が困難なケースもあるようですが、ビジネスモデルを確立させることが重要です。
また、「事業承継」は多くの小規模事業者にとって大きな課題となっています。後継者難倒産件数は比較的高い水準にあります。事業承継・引継ぎ支援センターをはじめとした様々な支援機関がサポートを行っており、こうした支援機関の活用が取組の推進につながる可能性があります。地域への思いを受け継ぎ、支援機関のサポートで事業承継を実現した事例があります。 「創業」を考えている方も、資金面やビジネスコンセプトの立案などに課題を感じ、起業に踏み切れていない様子が見られます。商工会・商工会議所や地方公共団体などが事業計画のブラッシュアップ、税務・法務関連の相談、創業のための出融資等、多様な支援を提供しています。一人で悩まず、専門家に相談することで道が開けるはずです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今後、お客様にもわかりにくい資料や冊子をまとめて、わかりやすく情報提供する際にも利用できそうです。
それでは、また。
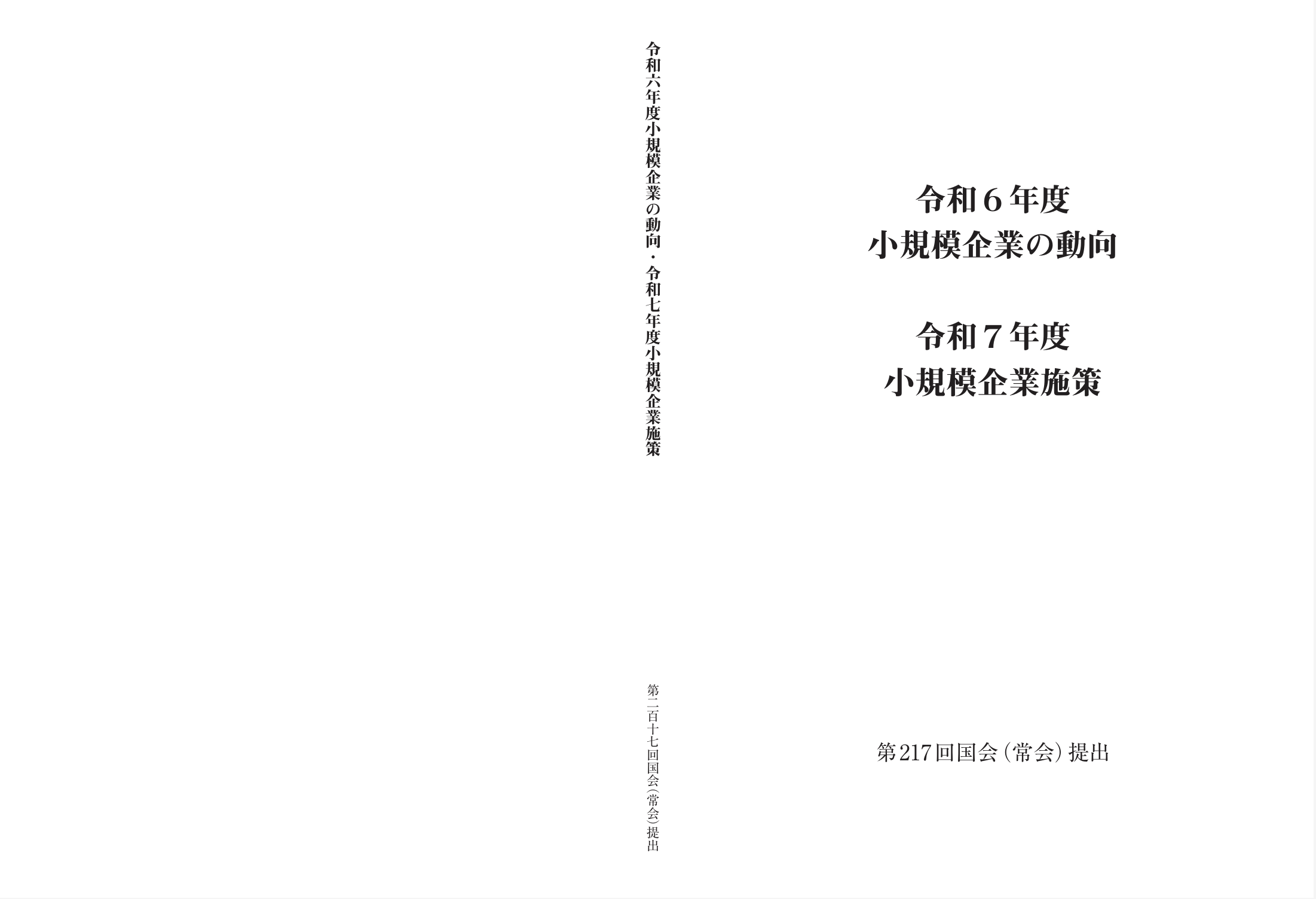
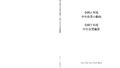

コメント